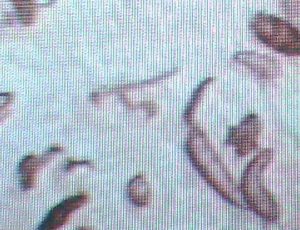投稿日:2003/04/26(Sat)
Q:31 私は3年前に定年退職をして、現在、シルバー人材センターで先輩の手元で、剪定の仕事を習っています。
剪定の書物には、外す枝として、逆枝が書かれていますが私は、逆枝であっても、枝棚にポッカリ穴が開いたり
盆踊りの「うちわ」のような形の枝になるよりは良いと思い残しておくと、先輩がいずれ外さなくてはならない枝だからと 手直しでパチパチ、パチーンと外してしまうのですが納得できません。
他の芽吹きの良い樹木は別として松は、懐に、芽が出来るまで残しておくべきだと思いますが,いかがでしょうか。
A:おっしゃる通り逆さ枝であっても残すことはあります。教科書通りにやっていたら風情も何もあったもんじゃありません。あなたの疑問はもっともだと思いますしその信念は大事だと思います。
しかし、親方にも親方の信念があり実績に裏付けされたモノでしょうからそちらも正しいのです。その現場に居合わせてお二人の問答に立ち会えれば私の意見を述べることはできますが、お話しだけでどちらが正しいとは申せません。その木のその場合がどうであるかですから。
出来うるならば、あなた専用の木を毎年手入れしてみればいいんですが。毎年あなただけがその木を手入れし、どう鋏を入れたかをきちんと記録し翌年もその次もそのデータを取っていくのです。想像だけで切り方を判断してはいけません。こう切ったらこうなるハズだなんていう何の根拠もない漠然とした判断をするくらいなら実績ある人の意見を受け容れるべきだと思うのです。最低3年間その木と向き合ってあなたなりの答えが出れば、それはあなたの切り方の信念として胸を張って良いことだと思います。
私はそうやって自分の剪定法を確立してきたつもりです。毎年同じ木と向き合うことで3年前、5年前の切り方が正しかったのかどうか木と語りながら自分なりの「正解」を見つけてきたのです。「正解」は教科書でも親方の胸の内でもなく自分自身の中にあるのです。
切り方にいつも迷いがあれば「正解」は見いだせず行き当たりばったりのその場しのぎの剪定になります。その場しのぎの手入れからは良い木は生まれません。剪定とは「正解」に向かって木を造り上げていくことだからです。
初期(修行)段階で自分担当の木を持てるかどうかが重要なのですが、多くの場合新人にそういうチャンスはなかなか与えられません。それにチャンスが与えられていたとしても時間に追われケツを叩かれての毎日の作業の中では「デジカメとノート片手に」なんて余裕も、またそうしなければという必要性も感じられないでしょう。
でも気持ち一つじゃないでしょうか?先輩が手直しされる前にちょっと写真を撮らせて貰い、一部は自分のやり方を残しておいて貰うように頼めれば、それらの経年変化を実際に比べる事が出来るのです。実績を積むとは具体的にはそういうことです。そういう行為を嫌がる親方も多いでしょうから難しいかもしれませんがね。
私よりずっと年上のあなたに向かってこんな講釈は失礼だとは思いますが、人生については勿論あなたの方が先輩に決まっていますが、人のエキスパートな部分に上下は無いと思いますので偉そうに語らせて頂きました。
結論として、逆さ枝だから全て切るとは限らない という考えは正解ですが、その木に関してそれが正解であったかどうかはわかりません。あなたが親方でない以上は、親方の「正解」が答えとして優先されるのはいたしかたありません。それが納得できないなら私のように独立して自分が親方になるしかないんです。
最終的にはお客様がどの「正解」を選ぶかによって親方達はそこで淘汰されていくわけです。